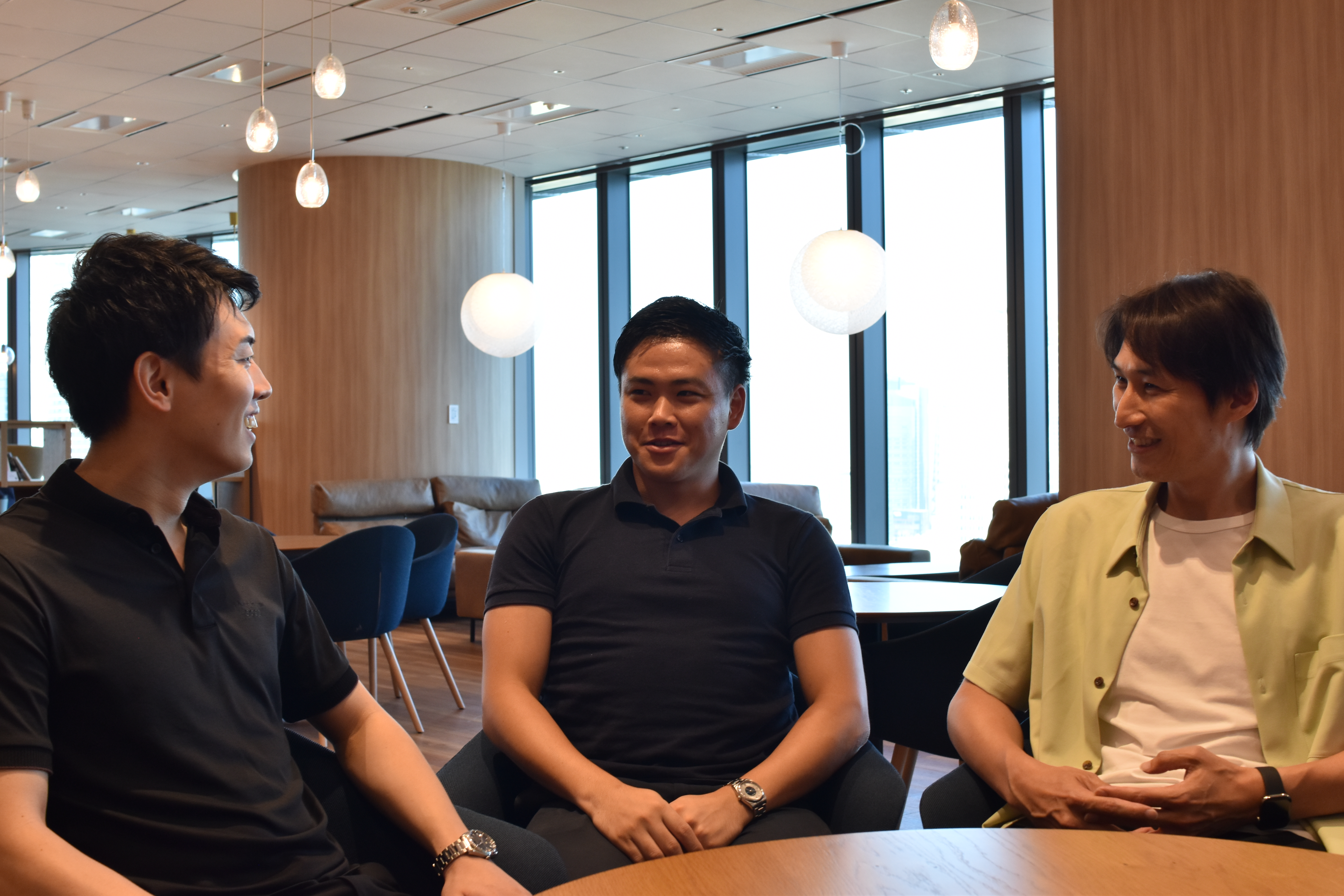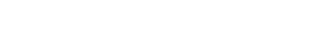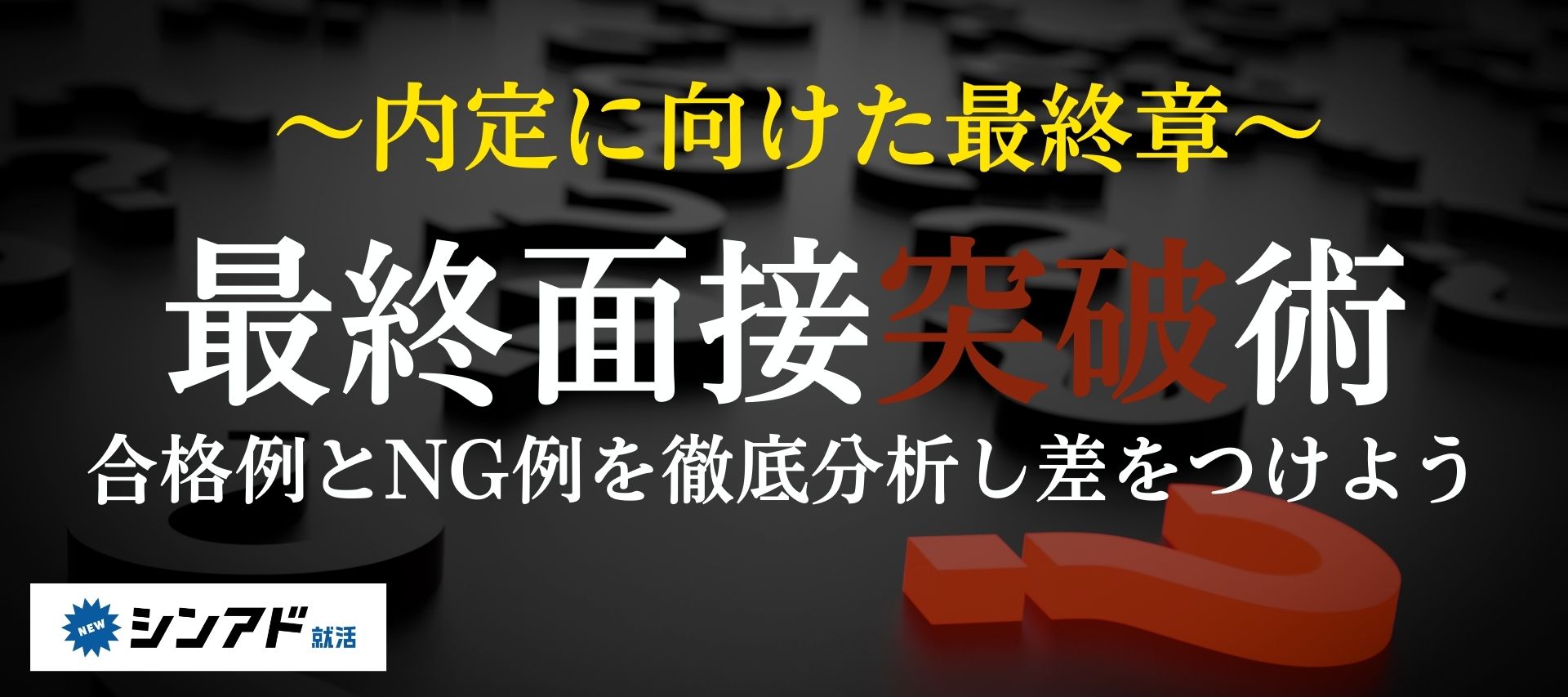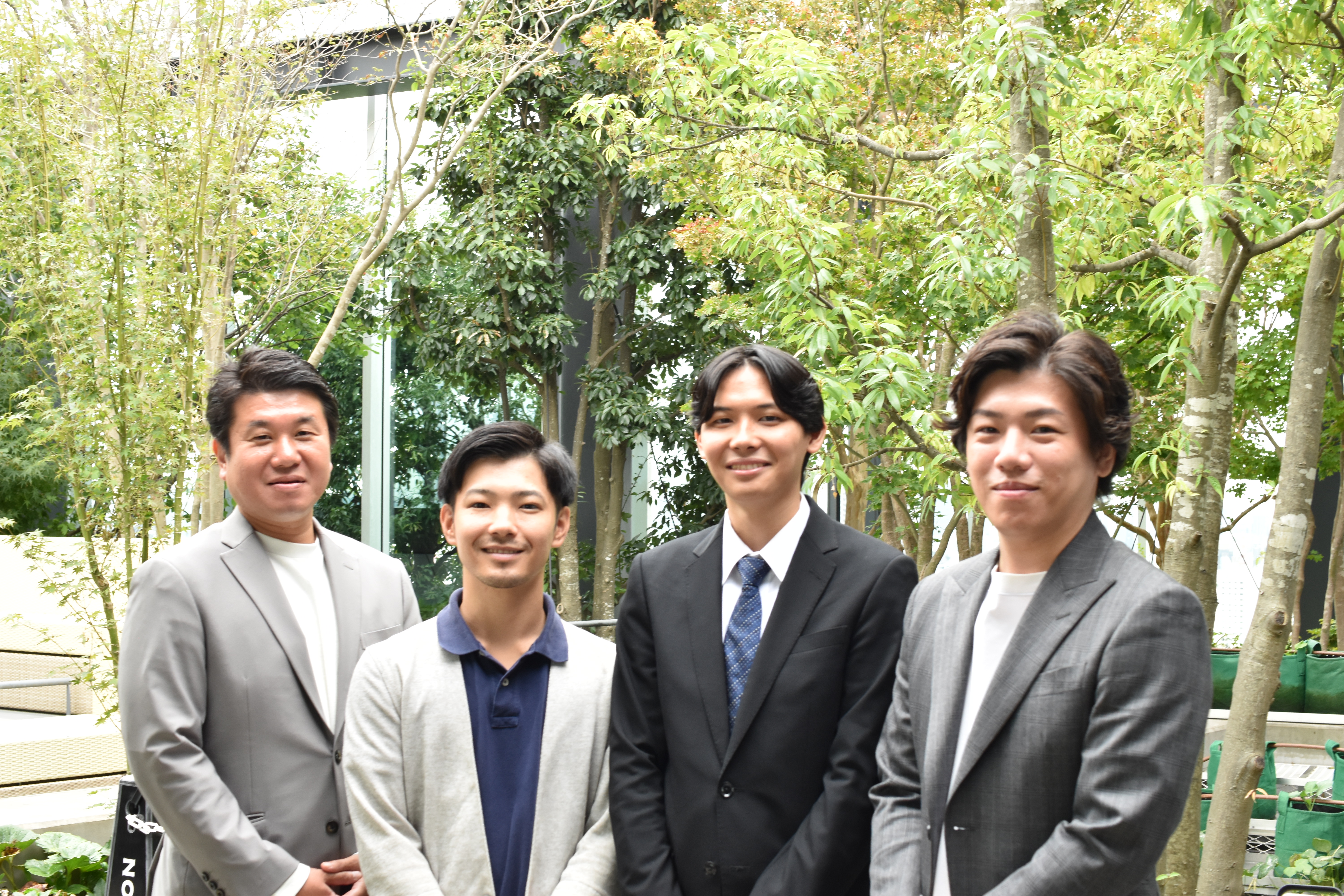目次 [非表示]

DX支援を主軸としたコンサルティング事業をワンストップで提供し、企業と伴走することでさまざまな変革を起こしてきた「プロジェクトホールディングス」。
「プロジェクト型社会の創出」をミッションに掲げ、自ら考え行動するプロジェクト型人材を輩出してきました。企業を変革する多様なソリューションを提供することで、顧客1社1社を次世代を代表する企業へと導き、衰退する日本社会全体の復活を目指しています。
グループ内の中核事業会社「プロジェクトカンパニー」は単なるコンサルティングにとどまらず、経営者の視点を持ち、自ら事業を創出することもあります。圧倒的な成長環境の中で1年目から求められるものとは。そして今の学生に求められる心構えとは。
最年少で執行役員に就任した日野さん、社内事業立ち上げの中心メンバーである金井さんのお二人にお話を伺いました。

〈プロフィール〉
“DX”の先にある、本質的な変革とは。
--------DXに関わるサービスを多角的に支援されていますが、改めて事業内容をご説明いただけますでしょうか。
日野:DX領域を中心としたコンサルティング事業を展開しています。お客さんのもとへ深く入り込んでヒアリングしたニーズに応じてソリューションをワンストップで提供しています。ただあくまでDX支援というのは私たちの仕事の本質ではないと考えています。
--------就活生にとってもDX支援という言葉を目にする機会が増えたと思うのですが、本質ではないというのは?
日野:私たちが一番やりたいことはあくまで「お客さまの成果を上げる」ことです。お客さまと伴走して事業を改善し、変革を起こすまでやり遂げる。戦略の立案で終わるのではなく、実行のところまで添い遂げる。ひとつ実行して終わりではなく、課題に向かい合い継続的なソリューションの提供を行っています。DXはそのための手段の一つに過ぎません。
金井:すでにデジタルIT系の業界の中ではDXという言葉自体も旬を過ぎたと思います。日野が言ったように、その本質はトランスフォーメーション(変革)だと思います。AIを含むIT技術が急速に進歩する中で変革しなければいけない環境だからデジタルなだけであって。本質である変革を起こすために徹底的に伴走できるのが私たちの強みじゃないでしょうか。
--------コンサルティング業界を目指す就活生は「伴走型支援」という言葉もよく目にすると思います。御社における伴走型支援はどのような形で行われているのでしょうか。
日野:一般的に言われる「伴走型支援」も蓋を開けてみれば、単なるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング:業務の設計・運用を外部へ一括して委託すること)でしかないケースもあります。そうした企業と比べると、私たちはお客さまとの向き合い方や関与の度合いの深さが全く異なるものだと思います。
私たちはBPOではなく、お客さまの部長職以上の方々と直接議論を重ねながら目標達成のためにやるべきことは何でも一緒にやりますから。
金井:「事業を変革させよう」と決めた時に大きくやることは2つに分かれます。一つは伸ばす方法をどう考えるか。もう一つはどうやって削るか。削る方法を考えるのはいろんなコンサルティングの会社さんが得意だと思います。第三者目線で冷静に赤字部門を切り離していけばいいだけですから。
一方でプロジェクトカンパニーが得意としているのは伸ばす方法を考えることです。既存事業を伸ばすのか、新技術の開発を目指すのか…方法自体はさまざまな分岐がありますが、一般的に「削るイメージ」を持たれるコンサルとは根本から違うのかと思います。
自ら考え、自ら行動する「プロジェクト人材」へ。
--------お客さまへ寄り添うためにも「プロジェクト型人材」の存在が必要ということでしょうか?
日野:そうですね。先ほど申しあげたBPOのようなコンサルの在り方は「タスク型」だと思っています。お客さまの言われたことを丁寧にやりますと。
逆に、私たちはお客さまと一緒に結果を出すことが最優先です。言われてなくても改善のためにはどんどん提案するというスタンスが私たちが定義する「プロジェクト型」だと思います。
できる・できないの個人差は当然あるとしても、結果を出すために自ら考えて自らやるべきことを定義していくという意識は全員に求められるものですね。
--------そうした人材が揃うことでミッションである「プロジェクト型社会の創出」も実現できると。
日野:日本社会が高度経済成長期で発展を遂げたのは、日本人が「タスクをこなすこと」に長けていたからでしょう。それに特化していたからこそ、品質の高い車や機械を正しく作れたことが当時はバリューだった訳です。しかし、テクノロジーが進化する中でその作業は誰でもできるようになってしまった。
一方でアメリカでは、今この世の中にないけれども必ず必要となる革新的なモノを作り上げてきました。市場のニーズをしっかり捉えて、どう解決するかを定義した上で、その手段まで辿り着く力。まさに“プロジェクト型人材”の有無こそが、日米の差を生んだ要因だと思います。
私たちはそうした人材を今の日本に数多く輩出していきたいと考えています。彼らがリーダーシップを発揮し、事業活動を営んでいる状態こそが「プロジェクト型社会」だと考えています。
--------お客さまの課題に寄り添い解決するとなると、その領域や業界も広範囲に及ぶかと思われますが。
金井:おっしゃる通りお客さまが抱える経営課題に応じるために、業種や内容、規模や期間も多岐にわたります。わかりやすい最近の事例では、上場企業のマーケティング戦略方針の見直しがあり、3桁億円の予算規模で依頼されていました。
--------3桁億円と聞くと具体的にどのような仕事をするのか、学生さんには想像がつかないかもしれません。
金井:あくまでプロジェクト全体の予算ではありますが、一番最初にやったのは「合宿」でした。お客さまの部長役員と一緒に半日ほど時間をいただいて。既存のマーケティングデータをすべてひっくり返して、何が起きているのかをホワイトボードに書き出していく作業です。なぜこの施策をやっているのか。施策の根拠や理論は何だったのか。会社の現状はそもそもどうなっているのか。
分析の解像度を上げるとともに、初期仮説を立ててはその場で判断してもらい、意見の交換を重ねました。どういう道筋が良いか初期仮説が定まれば、あとは数字を使った分析ですね。どの戦略を取ると市場がどう反応するかすべて仮説を数字で証明しながら戦略を決めていく訳です。最初の合宿から役員の方々に提案し、了承をいただくまで約2ヶ月間とスピード感のあるプロジェクトでした。
成長は“打席に立つ”ことから始まる。
--------1年目からそういったプロジェクトに関わっていくのでしょうか。
日野:もちろん規模や内容に違いはあると思いますが、1年目から先方の部長職以上の方々と対話しながらプロジェクトを進める機会は与えられます。
コンサル業界に限らずですが、大企業であればあるほど若手の頃は実践の場に立てない。せっかく大手企業に就職したのに「お客さまの顔は見たことない。パソコンでシステム画面をずっと見てました」なんて話もあるくらいです。そういった環境下ではなかなか成長できないと思いますよね。
これを読むみなさんは就職活動でたくさんの選択肢と情報の中から”正解っぽいこと”を探そうとするんじゃないでしょうか。ただ、キャリアに“正解”があるなら、すべての社会人が成功しているはずです。大切なことは自分が社会に出た後も、生きた情報を取り続けることです。そういう意味で打席に立つ経験が絶対に必要だと考えています。
いろんなお客さまに自分自身の言葉を使って、情報を引き出すための対話を重ねることで見えてくるものが必ずあります。だからこそ若手のうちにそういう経験をちゃんと積んでほしいと考えていますし、それが他の企業とは違う決定的な差になるんじゃないでしょうか。
金井:ひたすらに実践経験を積んで「理論」ではなく「持論」を持てるようになる必要がありますね。理論は今の時代調べればすぐに出てきますが、それは抽象化された一般論です。本当はその理論を作るまでの過程における経験が大事で、それこそが持論になる。理論と持論が結びついて、初めて自分の力になる訳です。
そして学生と社会人では経験値を積むためのルールも変わってしまうんです。20年以上の学生生活の間は授業でインプットして、テストや課題でアウトプットをしますよね。しかし、社会人になった途端、アウトプットをしない限りインプットが返ってこない状況になるんです。自ら行動を起こさない限り、誰もフィードバックを与えてくれません。このルールの違いに早く気づいて、自らアウトプットを頑張って出せるように自分を持っていく必要はあるでしょうね。
挑戦を続ける人だけが見える景色。
--------将来を考える上で大切な話だと感じました。ついつい楽な方へ逃げてしまいたくなることも就職活動中は多くあると思いますが…。
日野:大学受験の時だって何時間も机に向かって頑張った経験をみなさんも持っているはずです。それがすごく苦しかったから、その頑張ったことを糧にして「憧れの社会人」になれるかというとそんなことはあり得なくて。過去の努力だけで将来の果実・成果を得ることはできません。苦しいけれど今頑張らないとチャレンジした人たちに追い抜かれてしまうんです。
そして社会人生活の方が圧倒的に長い時間を過ごす訳で。上に行くほど、より大きな責任と挑戦が求められます。
--------厳しい言葉ながらそのマインドを持てる学生さんはプロジェクトホールディングスで伸びていく人材なのだと感じますね。
金井:一つマインドセットの話をすると、効率を先に考え過ぎないようにしてほしいと思います。
分数に例えると、分母は実力値、分子はアウトプットの大きさだと思っているのですが、効率を重視するということは少ない分母から大きな分子を生み出そうとする考え方です。
でも、分母が1しかない人はどんなに無理しても2のアウトプットしかでないと思うのです。ですので、今は将来のアウトプットを高める為にも積極的に分母を大きくすることに時間を惜しまず、成長をしていくことが大事だと思います。
日野:就活生の方から「どんな専門性やスキルを身につけたら良いですか」と質問されることがあります。ただ確立された方法論なんてこの世にはありません。逆に言えば私たちはそんな方法論がないからこそ、スキルの有無を求めていません。ただ現代の社会構造というものをしっかりと捉えた上で「自分はやっぱり成長しなければいけないんだ」とか「チャレンジしたいんだ」と感じた学生さんにぜひお会いしたいと思います。プロジェクトホールディングスは、挑戦する人に“次の打席”を惜しみなく与える会社です。
その一歩を踏み出す勇気が、あなたのキャリアを大きく変えるかもしれません。
--------多くの就活生のためになるインタビューでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。